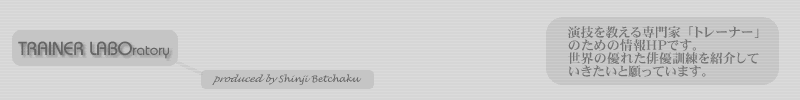スタニスラフスキー An Actor Prepares 「俳優修業」 の分析・研究
「My Life in Art」を1924年に執筆し、スタニスラフスキーは当時世界的に名が知れ渡っていた「system」についての本を出版する運びになりました。彼の考えとしては、「身体的」な人物形象化とともに、「心理的」な俳優訓練・準備について書くつもりでしたが、アメリカの出版社が、分割するよう提案しました。「心理面」と「身体面」を別々に発表することで、読者が誤解を持たないか恐れました。「心理面」「身体面」は一枚のコイン だと考えていましたから。しかし、しぶしぶその案に従うことになりました。かくして、「An Actor's Work on Himself in the Creative Process of Experience」と「An Actor's Work on Himself in the Creative Process of Physical Characterisation」の執筆が準備されます。スタニスラフスキーが、本全体の概略でも書いていればよかったのですが、書いていなかったために、その恐れは現実のものになりました。スタニスラフスキーは「メンタル面の人」「スーパーナチュラリズム」という印象を、最初の本が与えてしまい、大きな誤解を生む ことになりました。この誤解はロシア国内においても例外ではありませんでした。アメリカのメソッドも、旧知のスタニスラフスキーも、オリジナルのスタニスラフスキーの全貌から見ると、一部に過ぎない のです。英語版でさえ、このように問題が多いのに、それを日本語にした「俳優修業」が更に誤解を生む本になるのは当然 です。「俳優修業」は逐語訳になっているので、余計取っつきにくく、また専門用語をわかりにくくさせています。本当は、平易な形で、いかにも専門用語というように書いてはいないのです。しかし、英語版でそのニュアンスが専門用語的になり、日本語版で理解しにくい「超目標」や「単位」という言葉になりました。現在、英語のスタニスラフスキー研究本では、よりスタニスラフスキーが意図したであろうニュアンスの言葉に直されてきています。例えば「目標」である「objective」は、「task」という言葉になっているのをよく目にします。
誤解の多いスタニスラフスキーと「俳優修業」。このコーナーが、その誤解を解き、より明確・正確に理解する手助けとなればと思います。
コスチャ(Kostya)少年をメイン主人公に、演出家トルツォフ(Tortsov)の指導風景を通して、スタニスラフスキーは自らの考えを書きつづっているのが「俳優修業」の構成です。俳優初心者はとかく演じたがってしまい、すぐに結果に走り、プロセスを無視してしまう ということです。最初の授業での発表のため、コスチャは「オセロー」を選び、夢中になって真似事をし、大成功をもたらすと確信していました。特に、内面には目もくれず、外面の真似ばかりをしていたのです。そんな彼は練習ですぐに行き詰まり、演技の難しさを感じます。また、発表の時の厳粛な空気に萎縮します。スタニスラフスキーは、俳優入門者の立場に立って、得体の知れない演劇の魅力や、演技の深さをサジェストしているのです。
悲しいことに、日本で演劇を芸術と捉えて活動している人はどのくらいでしょうか。この章では、芸術であるという観点に立って、まかり通っている偽物の演技(俳優入門者にありがちの演技)を批判しています。インスピレーションや潜在意識の大切さを伝え、それが「役を生きる(living a role)」ことにつながる といっています。ここで間違えてはいけないのが、「なりきること」が「役を生きること」ではない ということです。だからこそ自分の感情を覚えていなかったコスチャを咎めたのです。役と自分の相互関係のなかで、潜在意識を導くのは意識だからです。これが一つめの偽物の演技「なりきること」が「役を生きること」だと勘違いしていることです。「役の具体化(representing a role)」 です。ここで述べていることは、外面の準備ばかりに長けて内面をないがしろにしてはいけない ということです。内面のリアリティーの充実を図ることが大切です。「機械的な演技(mechanical acting)」 です。
本物の感情から演技をするのではなく、あらかじめ決めた動きや台詞の喋り方、表情を再現するというやり方です。ポールがやった演技ですね。物真似は大事ですが、かなり研究して、生きた再現にならないと芸術にはなりません。本物の感情・経験から生じた演技ではなく、どこかで見た、ありきたりの紋切り型の演技を「ゴム版(stencils)」の演技 とトルツォフはいいます。印刷の原板のように、同じ物を繰り返し生み出すだけの悪い演技です。この種の演技に対してスタニスラフスキーは強い警告を与えています。「やりすぎの演技(overacting)」 です。これは機械的な演技のなかでも最悪の部類に入ります。オセローを演じたとき、黒人のイメージから、野蛮人のようにふるまっただけだったのです。「利用(exploitation)」 です。自分のかわいい手や足、美しさを見せびらかせただけの演技で、役とは関係なく、自分のアピールのために演劇が利用されてしまったということです。このような行為は、それを求める人たちを引きつけるが、芸術家はこんな虚偽の、創造の芸術とはかけ離れたやり方には、厳しい手段を取らなければならないと戒めています。
ロシアのオリジナル版では、この章のタイトルは「Action, If, Given Circumstances(行動、もし、与えられた環境)」 となっています。スタニスラフスキーを理解している人であれば、即座にこの三つが、密接に関わりのあるものだと気づくでしょう。演技の要素は様々あり、それらが相互に関係しているわけですが、この章では、特にこの三つをテーマとしています。「内的な行動(inner action)」 なのです。生徒たちの意識は、外面の動きにしかなく、トルツォフの演技がよかったのは、内面が正当化され、それが身体と結びついて自然な行動に表れていたからです。座っている演技や、動きがない演技でも、このことができていれば強烈に引きつけるものとなるということを教えているのです。内的動機(inner motives) または内的目的(inner aim) の大切さを語っています。行動には理由がなくてはいけません。また、ここでは外的要因についても語っています。つまり、その行動をするときの状況が変化すれば、その行動の意味もがらりと変わるということです。これらの理由を見つけて行動を単なる機械的なアクションとしないことを正当化(justification) するというのです。「もし(if)」 です。第四項・第五項はこの「もし」についての話です。「Magic If」 とも呼ばれるスタニスラフスキーの有名な用語ですが、考え方は簡単です。「もし〜だったらどうするだろう? 」と仮定してみることです。「〜だったら」には色々な当てはめ方がありますが、「もし自分がこの役の状況に置かれていたらどうするだろう?」とか「もしこの役の人物がこのような状況に置かれたらどうするだろう?どうなるだろう?」と、その役の「与えられた環境(given circumstances)」 や状況を分析した上で仮定してみるのが一般的です。従って、「もし」がスタートで、「与えられた環境」がそれを膨らませる素材というわけです。この「もし」を使うことによって、よりリアルなものを引き出せるようになります。
「システム」では、理解しやすいよう演技の重要要素に分けて考えていますが、完全に分離して考えることは無理で、この「想像力」 の中にも「感情の記憶」 や「適応」「途切れないライン」 など、他の要素と結びついています。この章では、「想像力は演劇のリアリティーを創り出すために非常に役に立つ手段」だとまず語っています。芸術家は、演劇だけの話ではなく、想像力が生み出すものなのです。「Magic If」 を使うよう薦めます。例えば時刻や状況を変えてみて、それを正当化しようとすると、様々なことが見えてきます。行動というのは、時・状況・場所に左右される ものですから。
4のところの冒頭の言葉は非常にわかりにくい翻訳になっていますが、ここでは要するに「劇世界の状況にも途切れない流れがあり、その状況の中にいる自分の中にも途切れないビジョンがある」ということで、この内的ビジョン(内的イメージ) は、役を取り巻いている環境を鮮やかに客に伝えたり、俳優の感情や気分を導き出してくれるのです。6つのクエスチョン です。①わたしは誰? 「超目標」 になるのです。
「第四の壁」についての話からこの章はスタートします。第四の壁とは、(プロセニアムの)舞台と観客を隔てる見えない境目のことです。役者は第四の壁に向かって演技をします。観客が観ているからです。しかし、観客を意識しすぎてしまうと逆に第四の壁は俳優を苦しめたりもします。見えないけれども恐ろしい存在であるわけです。フォーカスを、舞台より奥の客席に向けてしまってはいけません。注意の円(Circle of Attention) という用語が出てきます。スタニスラフスキーはわかりやすく捉えるために、小(the small)・中(the middle)・大(the large)・特大(the very largest) と分けます。注意の円(小) は、自分の身の回りへの集中です。これは、明るくても暗くても比較的集中しやすく、またその対象物への感情も沸き上がりやすいのです。感情が強ければ、集中度も高くなり、集中度が高くなればまた感情も強くなります。また、このときは「周りが見えてない」状態ともいえます。「靴のヒールをなくしたのは誰」と演出家が聞いて、みんなが探していると、誰もそのとき秘書が現れて書類を渡していたことに気づいていなかったというエピソードはこれを現しています。 注意の円(中) は、自分とその近くの環境であり、対話している相手なども中のレベルに含みます。身の回りにはたくさんの物があるために、焦点がぼやけやすくなるのは確かです。注意の円(大) は、ステージ全体を含みます。景色を見ながら歩いていたり、焦点がとても広がっています。トルツォフは、このエリアで、何かの対象物を注意させる練習をさせます。注意することは目を使うことであり、目は観客の注意を引き、イメージを共有します。 ですからとても大切なことです。これが演技調ではなく、自然にできなければいけません。注意の円(特大) は、舞台上だけでなく客席までを含めた最も大きなエリアです。この円は、観客を気にするということであり、これ見よがしの演技に陥る可能性が出てきます。
上記の内容は外的注意(external attention) ということになり、この逆に内的注意(internal attention) は、自らの内部に目を向けた集中で、五感や記憶、イマジネーションということになり、これは外的注意よりもより重要で、よく訓練されていなければなりません。イマジネーションの訓練と、これら注意・集中の訓練はとてもよく似たもので、どちらも毎日の生活から行うことが出来ます。しかし、意識的に行っていくには意思と目的意識と、忍耐が必要になります。そして、普段から自分の身の回りのことに注意を向け、想像力を使ってものを見るようにしましょう。
「An Actor Prepares(俳優修業第一部)」は、精神面を主に、「Building A Character(俳優修業第二部)」では身体面を主にスタニスラフスキーは書いていますが、ここでは身体面について触れています。しかし、単独に身体のことを述べているわけではなく、精神面が密接に関わっていることがうかがい知れます。身体が固くなった(緊張した)状態では五感や精神の働きが発揮されにくい ということを示しています。したがって、身体を適度な状態(過度に緊張していない)にしておく必要があるのです。俳優にとって必要なことは、緊張をコントロールして制御できるようにすること です。そのためには、自らの緊張を意識するよう習慣化させ、緊張を緩めるよう努力すること が必要だと説いています。コントローラー (ベネデッティ氏の翻訳では「モニター 」としており、こちらの訳の方が適切だと思います)」
は、自分自身に対して緊張を監視することもできますし、もちろん他人に対しても観察できます。このモニターを持って、立っているときや歩いているとき、なにかの動作をしているときの緊張の状態を確認する練習をさせています。自然な姿勢 と重心の移動 についても触れています。モニターによって身体を意識する習慣がついたら、正当化された自然な姿勢と、無駄のない重心の移動についても意識することができます。単独動作(isolated act) 」は、俳優の身体訓練のヒントを示唆しています。動かす身体の筋肉だけを使い、他はリラックスさせておくというものですが、身体の部分部分への意識を高めると共に、無駄な緊張を排除し、緊張と緩和をコントロールする練習になります。
一章で、七面鳥を使って非常にわかりやすく、「ユニット(Units) 」に分けることの意味を教えています。一つの作品をまとめて捉えようとすると無理があるので、ユニットに分けていくといいということがわかります。ユニットに分けてもまだ大きいようでしたら、更に細かく分けてみるといいでしょう。「単位」というルールや決まりはありません。「units」以外に「bits 」という言葉も使われますが、全体の中の小さな断片であるという認識で、その断片は全体があってこそ意味があります。作品へのアプローチの過程で便宜的に ユニットに分けますが、最終的には全て融合させて全体になります 。ユニットに分けず、全体から入っていくと、様々なディテールにつまずき、混乱し、全体像を見失う恐れも出てきます。戯曲のコア を探すと、ディテールに騙されずシンプル化することができます。コアとは、その作品にとって欠くことの出来ないもののことです。つまりは要点を抑えていくということです。そうすれば大きなユニットがわかり、次に中くらいのユニットや小さなユニットにも分割できます。
これらユニット分けで、絶対に忘れてはいけない大きな目的があります。それは、全てのユニットの核心にある「創造的目標(creative objective) 」です。目標と単位は有機的に結びついています。目標は、一貫した流れを持ちますし、単位と同じく大きい目標、小さい目標に分けられます。そして目標は内側からの能動的なもの であるべきです。すなわち行動を導き出す感情や意志を伴っていないといけません。
後半で、経験の少ない生徒に対して、まず身体的な目標に集中するようにさせています。これは、行動と心理は表裏一体ですので、細かい身体的な行動から、どのような心理や意味があるのかを見つけさせようとします。そして、目標を「〜したい(I wish)(I want) 」ということばに直すようにさせます。名詞ではなく動詞を使うのです。それによって、目標は動的になり、行動を導き出していきます。
他よりも長いこの章で、問題となるのは真実の感覚 です。例えば居場所のわからない財布を探すことは誰でも出来ますが、居場所のわかっている財布を、居場所がわからないという想定で探すとき、難しいと感じるものです。舞台の上で生きる(live) というのは理想的なことですが、演技の中で真実の感覚を持ち、そのキャラクターの生活を生きることは難しいです。この舞台上の真実(scenic truth) がテーマです。舞台の上の小道具や装置が実際の物でないにしても、人物のスピリットと内面生活は真実であり、また真実だと信じて演技をすることが大事なのです。正当化(justification) のプロセスが必要になってきます。「どうせこの剣はおもちゃだ」と冷めてしまったり、段取り通りに行動していたり、虚構に冷めてしまったりするのは信頼が薄いということです。真実の感覚を得るには信頼が必要です。 信頼とは信じ込む力です。これは俳優のみに限らず、観客にとっても必要な要素です。人は、真実の感覚と同時に不信の感覚(sense of untruth) を持っているものなのです。完全に100%真実の感覚でなくても、不信の感覚より高いパーセンテージとなるように心がけたいものです。「自分自身をチェックする意識」 が大切だと語っています。そこで、生徒たちは互いにどこがおかしくてリアリティーがなかったかを、稽古場でも生活上でもチェックすることにします。そうすると、揚げ足取りの批評にきりきり舞いとなり、余計に動きがとれなくなってしまい、トルツォフにたしなめられます。そして正しき判断、冷静さ、賢明さが芸術家の友だと教えます。そして、細かいあら探しにとらわれるのではなく、他人の良い所を見て真実の感覚を磨きなさいといっています。
第四章から問題にしているのは行動のフィジカルな面でのディテールです。いってみればパントマイムの正確さですが、紙幣を数えるなど何かアクションをマイムでさせたときにおかしい点がたくさん浮上するのです。実際の物がないことによって、多くの必要なディテールが失われていることに気づきます。そして細かいディテールに気をつけて行動すると、今度は一貫した大きな行動の流れが損なわれ、不自然なものとなってしまいます。細かいディテールも有機的につながって、自然でまとまった行動になっていなければいけない のです。そしてトルツォフは更に、行動の理由と背景に注意させ、正当化させるよう促しています。無行動(inaction) という課題が待っています。すなわち、喋らない、動かない演技です。そのとき、コスチャは機械的な陳腐な表現になってしまいましたが、動きがないときは感情の流れを押さえて正当化させなければいけません。内面では様々な動きがあるのです。
行動を導き出したり、正当化させるのは内面の感情です。行動(肉体)と感情・精神(魂)は相互作用して密接に関わっています 。「人間身体の生活(the life of the human body)」 と、「人間の魂の創造(creation of the human soul)」 が出てきます。ライフ・オブ・ザ・ヒューマン・ボディ は、行動の流れは、舞台上での断片的なアクションにとどまらず、その人の人生・生活という全てを含む大きな流れのなかの一部である ということです。そしてそれこそ、その人の魂の根本から創り出されるもの であり、それがクリエイション・オブ・ヒューマン・ソウル なのです。即興(improvisation) です。即興は大いに有効です。そして、どこから始めればいいのかのヒントとして、身体面・行動面からがよい ということがわかります。小さな身体的行動は大きな内的意味を持ったりもします。スタニスラフスキーはメンタル面のメソッドばかりが取り上げられて誤解を受けてきましたが、実際には身体面・行動面を非常に重要視 し、芸術的な表現へと昇華させる上で大事な基礎要素だと認識していました。「マジック・イフ(Magic If)」 や「与えられた環境(given circumstances)」 が、内面から確立された演技を創り出す基礎となっているというのです。そして、正しくその道に導いてあげるには、信頼の感覚と真実の感覚が必要なのです。
9章・10章では、インスピレーションで、役に入った状態になれば身体面・行動面は必要ないのではという疑問が提示されます。たしかにインスピレーションで、内面から感情があふれ出して行った演技は、観る人の感情を揺さぶる素晴らしいものとなりましたが、それを繰り返そうと思うと無理で、一回の奇跡で終わってしまったのです。そうならないためには、やはり身体面・行動面が必要になってくるし、次の章で出てくる「感情の記憶(Emotion Memory)」 が必要になってくるのです。
稽古というのは新鮮さとの闘いでもありますが、この章でのコスチャたちの演技は、先を知った演技になってしまい、行動の要因となる感情がなにもリアルではありませんでした。そこで、感情の導き方についてトルツォフから指導を受けます。いつでも自由自在に感情が沸いてきてくれるわけではないので、「与えられた環境」や身体面の計画などを使って、感情を導き出すためのアプローチが必要になるのです。「Emotion Memory(感情の記憶)」 は、過去の人生経験の記憶 と五感の記憶 、それから身体の記憶 に分けられます(身体の記憶は触覚でもあるので、五感に含めることも出来ます)。また、「俳優修業」の中では、「Emotion Memory(感情の記憶)」と「Sensation Memory(感覚の記憶)」の二種類の言葉が出てきますが、トルツォフも一緒くたになるというように、まとめて感情の記憶と捉えてよいと思います。五感の記憶を利用することで、演技の上でもリアルな感覚を持つことが出来ますし、また感情の記憶を刺激したりします 。
四章、五章で興味深い点は、感情の記憶が現実の出来事よりも強烈な感覚を導いてくれたり、芸術的な新鮮なインスピレーションを与えてくれるケースがある ということです。トルツォフは時間というフィルターを通すことで記憶が浄化したり、詩的に変わったりすると述べています。偉大な詩人や作家も、大規模な記憶の中から創造しているのです。だからこそスタニスラフスキーは、様々な人生経験の記憶を蓄えておいた方がいい と薦めています。
スタニスラフスキーに対しての勘違い、また演技に対しての勘違いで、「役に入り込む」「感情に没頭する」ことが理想的だと捉えるのは間違っています。あくまで演技者本人がベースになっているので、スタニスラフスキーは、「舞台では決して自分を失ってはならない。いつでも自分自身を演じなければいけない 」と強く念を押しています。ただし、役のための準備をしっかり行うことは大前提です。
第6章では、外的要因(照明や音響効果、舞台美術など)が精神状態やイマジネーションに大きく影響するということを語っています。感情をどのように表現するのかとというよりも、感情を起こさせるための工夫が必要 なのです。したがって、「感情の記憶」とは、結果重視ではなくプロセス重視であり、感情を刺激してくれる要素が大事になるのです。
Communion(交感) とCommunication(意思疎通) は、似通っています。コミュニケーションは、言葉・ジェスチャー・表情 を使います。これは、俳優でなくても誰でも行っていることです。コミュニオンは、俳優の舞台上でのコミュニケーションや意識で、見えない意思疎通 だと考えられます。一章でトルツォフは、「他から吸収したり、自分を他に与えたり」することが舞台上で必要になるといっています。交感には感じるエネルギーや発するエネルギーが必要 なのです。これがなければ観客も注意して見てくれないのです。観客にエネルギーを与え、また観客からもエネルギーを受け取るという点で、観客との間にも交感するということが成り立ちます。
交感するのに必要なエネルギー。これを自分自身の中にも見つけることが出来るというのが、ヒンドゥー教のプラナ の話でしょう。身体の中心に、エネルギーの源があり、それは感情を放出する力があるようです。魂(spirit)という言葉を比較的よくスタニスラフスキーは使いますが、その中心エネルギーを彼は実感しているようで、それがプラナと通じるのでしょう。
見せかけの形だけの演技では、相手役との交感もできないし、観客にも伝わりません。この「Communion」の章でも、入念に注意がなされています。これ見よがしの形式(the form of exhibitionism)は、よく使われ、また人気があるというのは認めているものの、決して真の俳優はこの形式に陥ってはいけないと口を酸っぱくしていっています。
最後のほうの章で出てくる「放射・放出(irradiation)」 と「把握(grasp)」 は、「交感」とほぼ同じです。交感の際に、放出しているエネルギーが、「放射・放出」であり、それは相手役や観客を引きつける力を持っています。それが「把握」です。「把握」というよりも「つかまえる力」という意味です。ちなみに「把握」は、スタニスラフスキーはめったに引用していない言葉ですが、15章において創造における重要な三つの点として、その一つに「内的把握(inner grasp)」 を挙げています。
Adaptation(適応) は、CommunionやCommunicationと似ている単語のため、わかりにくい印象を受けるかもしれません。適応や適合という言葉は同じ種類としてスタニスラフスキーは使っています。人と人との様々な関係に合わせるための内的・外的手段であり、また自らの目的を成し遂げる手段 といっています。俳優は様々な点で、合わせることが必要になります。それは相手の行動や言葉に対してかもしれないし、その場の状況かもしれません。何かの目的を達するために行動していくときにも必要です。自分とその周りに対して、バランスを取りながら合わせていくこと が適応だといえるでしょう。バランスを取りながら合わせるということは、ふさわしい行動や交感をする ということでもあるのです。鮮明さ・多彩さ・大胆さ・繊細さ・微妙な陰影・優美・風情 といった要素があると述べています。無意識に適応できることが素晴らしい と見なしています。そういった意味で、思いがけなさ(unexpectedness) は力を持っています。直観的な適応(intuitive adaptation) ができるようになるためにはどうすればいいのでしょう。
潜在意識に訴えかけ、その直観的な適応を導くことはとても困難なことです。なぜなら意識下にあるわけですから。そこでスタニスラフスキーが薦めているのは、毎回違う適応を見つけ出すという手法の導入です。これは意識的になっても無意識的になっても気にしなくてよいのです。新しいものを見つけようとする姿勢 が大切なのです。ここで述べているようなことは、スタニスラフスキー自身、即興(improvisation) を取り入れる中で、毎回新しいものを発見する試みをしています。
この章は、非常に短い章ではありますが、後半だけあってとても重要です。演技の要素をこれまで学んできて、楽器は出来上がったと言っていい俳優たちにとって、その楽器を演奏するためのキーは第1に感情(feeling) であり、第2に精神(mind) であり、第3に意志(will) であると語られます。この三つは、いいかえれば心・脳・身体 ともいえます。意志(will)というのは、わかりにくいですが、行動を導き出す欲望(desire) と捉えてもいいのです。欲望や願望は行動を必要とします。ですので、意志を実行に移す身体は必要になるのです。感情 はどうあっても必要なものだとわかるでしょう。その感情を導き出したり、新鮮な創造的な演技に変えたりするのには精神 または知性 が必要になるのです。そして、欲望や願望となり行動を導き出す意志 。この三つをスタニスラフスキーはマスター(master) と称しています。そして三つは相互に結びついており、いつでも相互に作用し合うのです。これら三つのマスターを駆使できるようになれば俳優として理想的と言えます。目的(objective) の話にも触れています。これは第15章「The Super Objective」で大きく取り上げる要素ですが、目的が意志や感情を直接的にも間接的にも刺激することは間違いないといえるでしょう。バランスも大事 なのです。
舞台の稽古に臨むとき、最初にテキストを受け取ってから、どのようなアプローチをしていくでしょうか。まずはテキストをよく読み込んで、解釈する必要があり、いきなり役の本質をつかんでその役の感情や精神を思いのままに出せるということは極稀なことです。テキストを様々な視野から分析し、読解することで、漠然に広がっていきます。我々はこの中に途切れぬライン を見つけなければいけないのです。このラインは生きている人間のライン ですが、行動のライン と、感情のライン の2つに分けて見ることもできます。
一日の生活を追って考えてみたとき、短いライン(行動)が連なり、過去から未来へと続いていきます。短いラインがポンとある場合もあれば、幾つかに連鎖している場合もあるでしょう。そしてそれらのラインはその時々の感情や意志といった内的原動力が導いているのです。常に行動と感情は表裏一体 です。全体の大きなライン をつかんでおきたいものです。
俳優と演技における様々な要素を学んできましたが、それらをひっくるめて舞台で実現できる創造的状態が自分自身に出来ていないといけない のです。人間なので、気を抜くとたるんでしまったり、積み重ねてきた創造状態を忘れてしまったりします。日によっては調子が悪い、気分が乗らないということもあるかもしれません。しかし、それではいけないのです。楽器であれば、音の調子が悪ければ楽器を手入れすることで改善するかもしれませんが、俳優は自分自身の心と身体を、最適な状態にもっていかなくてはいけないのです。
Inner Creative State(内部の創造的状態) は、Natural State(自然な状態) と非常に近いといえるでしょう。その自然な状態をつくり、キープすることが舞台では難しいのです。わざとらしい演技や、誇張した演技、自己顕示の演技でごまかすことはできません。真実の演技、自然な状態 というのは実に難しいことなのです。俳優はより熟練すればするほど、自然な創造的な状態で舞台に臨めるのです。
スタニスラフスキーは役の準備について、こういうことをいっています。登場の二時間前には来て準備を始めなさいと。そしてまず身体の緊張と固さをほぐし、次になにか対象を選んで様々にイメージを巡らすイメージ・トレーニング、その次に注意の円を自分の小さな範囲の中で作ってみます。自分とその対象物です。最後に目的を一つ決めて、その動機を考え、行動してみます。変化もあっていいです。注意の円は、移り変わったり、大きくなったりしています。俳優は、舞台で、生き、泣き、笑い、しかもその間中、彼は彼自身の涙や笑いを見ている。この二重機能、役と自らの間のバランスが己の芸術をつくっているのだ 」
スタニスラフスキーの中でも殊更有名なスーパーオブジェクティブ(超目標) 。Jean BenedettiはSuper Taskという英訳のほうが良いとしていますが、Super Objectiveという言葉が既に有名になっています。全ての目的を内包する極めて本質的な目的で、あらゆる大きなユニット、小さなユニットを含んでおり、これは作家の創造的な魂でもある ことがわかります。
スーパーオブジェクティブの使い方は、「わたしは〜〜したい」 という言葉で表します。ハムレットであれば「父の復讐を成し遂げたい」でしょう。これはハムレットという作品通じて貫通している軸となる目的です。ただ、面白いことに、このスーパーオブジェクティブであれば、力強いハムレットを想像できますが、「苦悩をなんとかしたい」という言葉で使うと、これも作品通じて軸となりますが、人間の弱さと葛藤が前面に出たハムレットが想像できます。従って、どのような言葉で表すかで、全体的な演技が変わってきます。
第二項ではスルーアクション(貫通行動)(Through-Action, Through Line of Action) について述べています。スルーアクションは様々な小さな目標で構成された演技の流れであり、この流れはスーパーオブジェクティブの方向を向いています。この流れが、あちこちに向いていたり、スーパーオブジェクティブと全く関係のないものだらけであれば、良くない作品、良くない演技といえるでしょう。
作用(action)、反作用(reaction)のくだりは、理解しづらいかもしれません。戯曲というのは、優れた作品ほど大きな葛藤を孕んでいます 。ハムレットがいとも簡単に復讐ができれば、ドラマにならないのです。簡単に彼のスーパーオブジェクティブを達成できない、障害や葛藤や反対要素が存在します。また、正義という要素があったとしたら、必ずどこかに悪という要素があるでしょう。ギリシア悲劇やシェイクスピアなど、優れた作品であればあるほど、対極要素があります 。
「システム」の創造過程における三つの重大要素はこれです。①内的把握(inner grasp) ②行動の貫通線(through action) ③超目標(super objective)
ここまで語って、「俳優修業」でのシステムの学習はほぼ終わりを告げるのです。
〔まとめとしての参考資料〕
「俳優修業」では「潜在意識閾(いき)」とやたら難しい言葉を書いていますが、「潜在意識の領域を目指して」という意味です。「俳優修業 第一部/An Actor Prepares」の最終章となります。潜在意識 というのは俳優の経験がものをいう要素で、教わって理論的に習得できるというものとはちょっと違います。しかし、システムによって、自発的な創造性を導いてあげることは可能です。
潜在意識の領域へ導くには、意識のテクニックによって、潜在意識を刺激する のです。
「俳優修業」の1節では、小難しい言葉が並んで説明していますが、要するに、これまで学んできたことを実現させることで、素晴らしい潜在意識の領域へ、より力強く扉を開けられるということです。
キーワードとして大事なのは、信頼と真実の感覚 です。潜在意識の領域は、突然現れたり、突然消えてしまったりします。
2節で、緊張の緩和のくだりが出てきます。潜在意識の領域へ近付くには、意識と技術の力なくは不可能ですが、真面目に意識しすぎるのもうまくいかないということがわかります。余計な意識を取り除き、自然と、自分自身が存在しているという感覚(「I am (being)」)ができてくると、自分自身の状態など様々なことが見えてきます 。「I am (being)」の感覚 (俳優修業では「われあり」という訳)のためには、緊張の箇所を見つけて緩めたり、注意の対象を見つけたりといった、これまでの技術をちゃんと利用します。それがインスピレーション となり、そして、役の人生・生活を生き始めたら、そこは潜在意識の領域 です。曖昧さ・不相応・頑張りすぎ を挙げています。
曖昧さは、不明確さや不安から出てきます。不相応は、自分の外見や年齢、性格とあまりに異なる役にチャレンジしようとすると演技自体は紋切り型になりがちです。頑張りすぎというのは、あまりに真面目に考えすぎたり、あまりに努力しすぎたりして息を切らすケースです。
逆に、障害ではなく、潜在意識の領域へと辿り着かせてくれる助けがスーパー・オブジェクティブ(super-objective)と、行動のライン(through line of action) であると述べています。劇世界では、様々な小さな目標が変化に変化を重ねて生まれてきます。それらはより大きな目標に吸収され、行動のラインに沿って進んでいくのです。スーパー・オブジェクティブ を考えてみましょう。そうすると、各場面を強める手助け となります。最終局面であるゴールへと進む力が強くなります。場合によっては、当初考えていた小さな目標が意味をなさなくなり、別の意味が生まれることもあります。潜在意識が自然とスーパー・オブジェクティブにそった意味を生み出します。
スーパー・オブジェクティブには、感情的な目標、意志に基づく目標、真実や信頼の感覚を満足させる目標、クリエイティブでイマジネーションを刺激する目標、これらは必要な要素です。そしてまた、劇作家の意図とも調和していなければいけません。スーパー・オブジェクティブと行動のラインに集中すれば、あとは自然に、潜在意識が働き、インスピレーションが与えられ、役を生きることができる でしょう。本物の人間、本物の生活が舞台上で繰り広げられるということは、まさに生きた芸術です。
俳優の創造は、人間の誕生と同じ。劇作家が父親、俳優が母親。子供が生まれるべき役。演出家は仲人のようなものと最後に書いています。人生と同じように、出会い、知り、仲良くなり、喧嘩し、お互いに手を取り合い、結婚し、子供を生む、と。
「俳優修業 第一部 『An Actor Prepares』 終了」
*ロシアにおいても、「メンタル重視」「スーパーナチュラリズム」をスタニスラフスキーシステムとして指導する人が多いといいます。
だから、ロシア人だからといって、本場のスタニスラフスキーシステムの人だと思いこまないように注意しましょう。
ここでは五種類の注意すべき演技を述べています。最も良くない四番目と五番目が、日本の小劇場によく見られます。三番目の「機械的な演技」は商業演劇のほうでよく見られます。
ぼく自身も使ってて困るのですが、日本語で考える「action」の訳、「演技」と「行動」は違います。このどちらを使うかによって受け取るニュアンスも違うと思いますが、ここでは「演技の中の行動・動き」だと思ってください。
やはり指導してきて、同じ事を感じることが多いです。立つこと・座ること・そこにいることができないのです。これは確かにレベルの高いことですが、それに気づかない人と気づく人との差は大きいです。
「俳優修業」がよくわからなかった人も、ここを読めば、スッキリ。
でも、山田肇訳の「俳優修業」の中では理解しづらい語句がたくさん出てきて頭を悩ますと思います。そんなわかりにくい箇所を教えてください。英語版と照らし合わせて、その意味を解説いたします。
質問の際は、「俳優修業」のページ数と、解説してほしい箇所を明記してください。betchaku@trainer-labo.com
実験をすると、視覚のイメージが得意な人、不得意な人、過去の記憶を頼りにイメージを広げる人、部分から全体にイメージを広げていく人など、タイプは人によって異なることがわかります。
想像力が豊かであればいいというわけではありません。論理 と一貫性 も大事です。ウケ狙いや自慢で、突拍子もないアイディアをたくさん出す人がいますが、それに原因や意味や正当性があるのか考えなければいけません。
公演の稽古で、私は「Q&A」 というものをやりますが、これも役者間で様々な質問をぶつけ、それに対して答えなければいけないというものです。それによって、役作りが非常に明確になるのです。
明るさ・暗さは、集中力に影響します。明るい部屋と暗い部屋で、なにかをイメージした演技をしてみたらすぐにわかります。また、壁が目の前にあるのにもかかわらず、その先に地平線が広がっているとイメージするのもまた困難です。実際に目に見えるものがある状態で、それに惑わされず自分のイメージを作ることができますか? なかなか難しいことに気づくでしょう。
「俳優修業」に出てくる「人前の孤独(solitude in public)」とは、小さい注意の円の状態で、自分のみに集中しているため、周囲の環境の中にいるにも関わらず、それらから隔絶されているということを表しています。
緊張は俳優にとって最大の敵です。しかし、全く緊張しない状態を目指してはいけません。適度な緊張が必要になります。
「姿勢」と「重心」については、たまたまこの章のなかに入っていますが、単独の章で紹介されていてもおかしくない重要要素です。
「ユニット」を定義しようとしなくて構いません。場合によっては小ユニット、中ユニットというように分けてもいいです。「俳優修業」で「段落」と出てくるのは、「division」の訳で、大きなユニットを指しています。
「objective」は「目標」という訳だけではわかりにくいです。「目的」「ゴール」「課題」という意味を含みます。
STONEψWINGSでは、「I want 〜したい」というエクササイズを行います。演出のプロセスで、俳優は自分のユニットを全て「〜したい」といいながら演技するのです。
「psycho-physical」 −精神と身体が有機的に結びついた状態−がスタニスラフスキーシステムの究極の理想形、Method of Physical Action です。
この「Emotion Memory(感情の記憶) 」について、Bella Merlinは、多くの実践者に誤解されていて、英訳版に関してもわかりにくいところがある述べています。
とりわけ、「感情の記憶は信じ込む演技である」という誤解を一蹴しています。
日本も同じですが、これ見よがしの形式の舞台が多く、また客が入ります。このような舞台が多いことは、日本演劇のレベルが低いことを示す一つの現象といえます。
STONEψWINGSの舞台の稽古でも取り入れている「I Do」「I Want」 は、まさしく常に新しいものを発見しようと繰り返し即興を行うスタニスラフスキーの実戦的手法です。
感情は、英訳がfeelingとなっているので、感覚を含むともいえます。しかし、emotionとfeeling両方の意味で捉えておくのが無難でしょう。
「役になりきる」ことが理想の演技だと勘違いしないでください。実際には俳優は自分の演技を監視し、コントロールしているものです。
俳優としてのこの究極の領域については、「Creating A Role(俳優修業 第三部)」のほうが詳しく探求して書いています。
スタニスラフスキーがこれらの技術に加えて、晩年重要視した方法は「インプロヴァイゼイション(即興)」 ではないでしょうか。
シアターゲームティーチャーやインプロティーチャーになるための養成講座もあります。